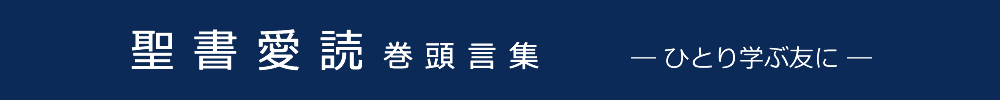
|
安息と吸収と清潔 |
|
極めて単純に人間の生態を観察しますと,適当な運動ないし勤労を含む心身の安息と,外部から空気や水や食物をとる吸収と,皮膚や血液や内臓の清潔とが健康の三要素といえます.病床にある人にとってはこの三つが主な仕事になります.幼児についても,ねる子は育つという安息に積極性を見る諺もありますし,しつけも吸収と清潔が自分で出来るようにというところにはじまります.古来川や海のほとりに文化が発達したのは水が諸生物の育成のもとになるからですが,それらを用いて人間が安息と吸収と清潔のために家や都市を築いて来たといえましょう.個人の住居で居間と台所と浴場が持つ意味も人間の生態という角度から考えるとあらためてその重要性が再認識されると思います. 聖書は安息を聖なるものとして保つべきこと,神とともに働く勤労のうちに真の安息のあることを教えますが,吸収と清潔もそれと結びつけられます.空論でなくて人間の存在そのものと取組むような形でその重要性が示されています.働くものがしばしの安息を与えられ,神を中心に平安に食をいただくこと,罪の汚れから解放されて聖なるものに迎えられて平安を恵まれ,そのしるしとしての洗いがあることなどです.いわゆる聖餐と洗礼の本来の意味がここにあります. 中世的な七つの秘蹟(洗礼,聖餐,堅振,悔俊,終油,品級,婚姻)が新教で聖餐と洗礼の二つにしぼられたのは聖書にこの二つが出て来るからですが,何故聖書にこれがあるかを考えなおす必要があります.形式化,律法化は聖書の伝統への逆行です.暦の上での安息日と聖餐と洗礼の結合は危険です.恩恵としての生態として,罪なき独り子を犠牲にして罪ある人を生かそうとする神の愛のあらわれとしての安息と吸収と清潔の意味をあらためて把握したいと思います. |