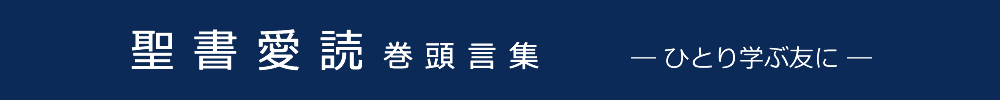
|
自由と平和 |
|
1960年6月にアフリカのコンゴがルムンバ首相の下に独立しましたが,間もなくカタンガ地方の分離から内乱となり,国連のハマショルド総長のあっ旋となりました.前者は政敵に殺され,後者は飛行機の事故でなくなったと伝えられますが,活動の目的としては,前者は黒人の自由のため,後者はアフリカの平和のためであったという見方が有力です. 自由と平和は微妙な関係にあります.第2次大戦で日本人は平和撹乱者の汚名を着せられましたが,戦後独立したアジアの人々からは自由の恩人といわれたこともあります.歴史の教科書によれば,1914年にオーストリアの王子夫妻が暗殺されたのが第1次大戦の発端ですが,事件が起きたボスニアのサライエボには当の暗殺者プリンチプの碑が立っていて,自由の英雄とされています. 個人も社会も,自由のためには平和を乱してもいいか,平和のためならば自由を忍ぶべきか,平和のためと称して他者の自由を奪うものがあった場合どうするか,等々の問題に直面せざるを得ません. 歴史はこのような問題で充満しています.自らの自由を主張して手段を選ばない場合に,平和はやぶれ,したがって自由そのものも失われる例は少なくありません.また,自由の戦士も多くは自らの自由を犠牲にしたので尊敬されるのですが,その目的が局部的な点に問題があります. 何といっても,最も低いものの自由を中心に全宇宙的な平和を示す聖書の真理は動きません.自らの自由を捧げ,罪なくして十字架につかれた平和の君イエスを信じ,彼に従いつつ神の国の完成を待つところに全人類の自由と永遠の平和が約束されているといえましょう. |