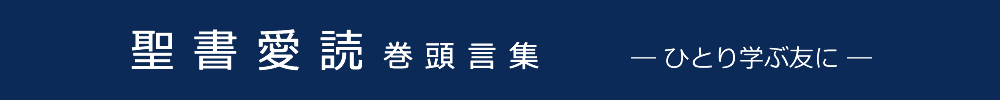
|
無から有へ |
|
何年か前,日本を訪れた数名の外人の学者と共同の研究会が行なわれたときのことです.日本人の研究発表には否定が多くて,そのことの本質や実態や対策に関する肯定的な表現が少ないことが指摘されました.not が幅を利かしていて,その後の but 以下の影がうすいのです.新聞の社説にも批判が多くて対案が少なく,国会の論議も学会の質問もそうです. 批判は必要であり,まちがいは何につけ除去されねばなりませんが,否定だけで終わる傾向は,東洋的な無の思想のためではないでしょうか.自然という長いものに巻かれるあきらめの虚無感につつまれていはしないでしょうか. 教育に際しても,いけないの連発だけでは子どもは伸びません.いいことを教え,それができたときに賞めて励ますことが親として必要ですし,そこに親子のつながりも深まります.親子ともに成長するのです. ほかならぬ無教会も,あれこれと否定や破壊をしつづけるだけでは,自分だけが救われるのを確信するパリサイ主義に陥って自他を滅ぼすことになります. 阿片化した宗教の恐ろしさを知るものには,聖書に親しんで福音を直接キリストから受け,平信徒として静かな信仰生活ができるさいわいの意味がわかるはずです.このよろこびが多くの人のものになるように,そして新しいエクレシアが建設されるように,この方向で祈りつつ進みましょう. 期待される教会像など人間の物さしによる結論でなく,与えられた恩恵の場所で神を讃美しましょう.病床が聖所となり,職場や家庭が祭壇となって,罪のゆるしの福音の力が発揮されているではありませんか. |