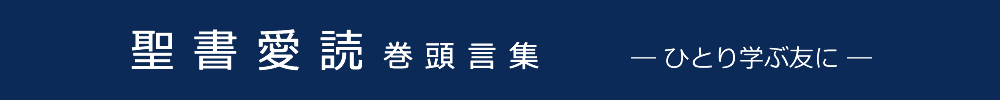
|
平信徒の世界 |
|
あるキリスト教団体に長年勤めた人が戦後政府の要職に迎えられて数年を過したことがあります.その仕事は難しい外国関係のことでしたから意味があったと思いますが,だいたい仕事が片づいてからもその人がキリスト教団体に復帰するまで時間がかかりました.わたくしもその団体から学徒としてときどき招かれましたのでその人とよく話しましたが,復帰をためらったのは,別に名誉心からではなく,役所の能率がよかったこと,いわゆる宗教とか信仰とかの美名のもとに誤魔化しがなされえなかったことによるということでした.その人は,ヤソは駄目ですな,と述懐していました. なるほど,学徒が団体の募金に奔走させられたり,十分学力があっても先生どうしの仲たがいのために学生の就職が拒否されたり,純真な信徒の心をこめた献金が一部の人の利益に悪用されたり,いろいろ困ったことがあるのですが,それが聖なるもののためということで済まされてしまいがちです.もとより,いわゆる俗世間にも悪いことがたくさんあります.しかし,そこでは悪を悪とする倫理的法則があり,聖なるものが担ぎ出されて誤魔化される余地がありません。そして変な宗教性のないほうが仕事の能率もいいようです.平信徒だからりっぱであるとはいえませんが,十字架による罪のゆるしを中間搾取なしに受けて,聖なるものを真に聖なるものとして心から崇める世界が与えられるのです. 祭司でなく建築家という平信徒であったナザレのイエス(マル6:3マル6:3 この人は建築家で、マリヤの子でヤコブとヨセとユダとシモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここでわれらのところにいるではないか」と。そして彼らはイエスにつまずいた。 )を救い主と信じ,テント造りをしたパウロ(行伝18:3行伝18:3 同業であったので、彼らのところに泊まって仕事をした。彼らの職業はテント造りであった。 )の手紙に教えられるさいわいをあらためて考えましょう. |