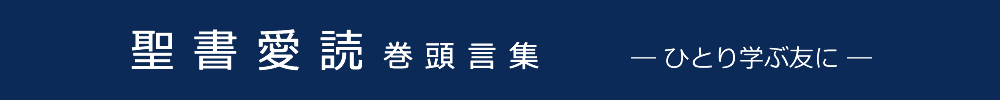
|
3つの“おし” |
|
戦前に書かれたある本の中に,海外旅行には3つの“おし”が必要とありました.第1は何よりもよく見ることで,オー・シー Oh, see! を心がけること,第2はなるべく黙っていて唖(おし)であること,第3に押しだそうです.いかにも軽妙な笑い草のようですが,長い外国生活やその後の旅行でもこの忠告はたびたび思い出してなるほどと感じました. 第1は百聞一見にしかずで,史家トインビーが,ある国の歴史を何冊も読むよりも,その国を一目でも見るほうがいいといっているとおりです.とにかく自分で見ることの大切さは,入学や就職の試験の時の面接の重要性にも通じます. 第2の唖については,いくら語学の達人でも母国語の人に比べれば高が知れていますし,下手なことをいうよりは唖で通したほうがいい場合はたくさんあります.外国にかぎらず,沈黙言語の効用は否定できません. 第3の押しは自己主張その他欲望の達成となると困りものですが,ぼんやりしていると置いてきぼりにされますから,存在を示すことも用事を催促することも必要です.とくに,こちらが誤解されたときは積極的に正すことが自他のためです. 聖書に信徒はこの世では旅人また宿れるもの(ヘブ11:13ヘブ11:13 信仰のうちにこれらの人々は死にました。彼らは約束のものを得ませんでしたが、はるかにそれらを見てよろこび、地上ではよそものまた旅びとと告白しました。 )とありますが,それはこの世をいいかげんにするのではありません.よりよい世界を仰ぎ見て,希望をもってその日その日を過ごすものにとって,このような処世訓も大切です.そして,最も深いところで,旧約から新約へと通じる神の救いの歴史の教訓がこれら実際的な現代的な教訓を生かして役立ててくれるといえましょう. |